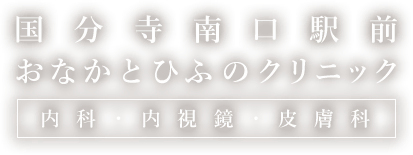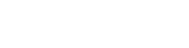体重減少とは(食べているのに体重が減る)
 体重減少とは、ダイエットや減量などの意図が無いにも関わらず、6ヶ月の間に5%または4.5kg以上体重が減ってしまった状態を指します。
体重減少とは、ダイエットや減量などの意図が無いにも関わらず、6ヶ月の間に5%または4.5kg以上体重が減ってしまった状態を指します。
体重は、食事などから摂取したエネルギーと消費するエネルギーのバランスが保たれている場合、維持されます。消費するエネルギーの方が少なければ体重は増加し、逆に消費するエネルギーの方が多ければ体重減少となります。
体重減少の原因としては、食欲の有無や筋力・筋肉量の低下、消化吸収能力の低下、水分摂取量の低下、基礎代謝の亢進などです。基礎代謝の亢進以外の場合は、食事を摂ってから排泄に至るまでの経路のどこかに問題が起こっている可能性が高く、消化器やその他内臓の何らかの病気によるもの、加齢による体力や筋力の低下、服薬しているお薬の影響、精神的な問題、社会的な問題などが考えられます。また、基礎代謝の亢進の場合も内分泌的な異常が考えられます。多くの場合は何らかの治療が必要になります。
体重減少
病気の目安
6ヶ月の間に5%以上体重が減ることで体重減少とされますが、さらに10%以上減る場合は実際に何らかの病気の可能性があります。
その際は、早いうちに原因を解明する必要がありますが、さらに20%以上体重が減っているようであれば栄養障害や何らかの病気による多臓器障害を疑います。
体重減少の原因
様々な原因から体重減少は起こりますが、原因となる病気などを見極めるためには、まずは食欲の有無と実際に食事を摂れているかどうかを確認していきます。
また、治療中の病気がある場合は、服用しているお薬が原因となることがあります。
さらに、高齢者は冠動脈疾患や加齢性の肺炎などの炎症性疾患、パーキンソン病などの神経筋障害や認知症といった基礎疾患の状態の変化、筋力や筋肉量の低下に関わるサルコペニアやフレイルなども原因となることがありますので、注意が必要です。
体重減少の原因として考えられるもの
- がん、特に胃がんや大腸がんなど消化器系のがん
- 胃・十二指腸潰瘍、慢性膵炎等の消化器病
- 細菌やウイルスによる感染症、自己免疫性の病気など
- 糖尿病、副腎や甲状腺の病気などから起こる代謝異常(高カルシウム血症、低ナトリウム血症などや、糖尿病性自律神経異常など)
- 抑うつ、うつ病など精神疾患
- バセドウ病などの甲状腺機能亢進症
- 糖尿病などの糖代謝異常
- クローン病などの消化管の機能低下や器質的な病気による吸収不良症候群
- 嚥下機能の異常・低下
- 口腔や顎の病気(口内炎や顎関節症などの他、入れ歯の不良など)
- 運動量やエネルギー消費が増加しているにも関わらず、食欲が出ない
体重減少の原因となりえる薬剤
- 心不全治療のための強心薬
- 喘息等の治療のための気管支拡張薬
- 血糖値を低下させる抗糖尿病薬
- 一部の抗うつ薬(体重を増加させるタイプもあります)
- 鎮痛薬、非ステロイド性抗炎症薬など
体重減少の治療方法
 原因となる病気が特定できる場合は、それぞれの病気に対する治療が最優先となります。病気が重篤な場合は、当院と連携する高度医療施設を紹介し、入院にて治療を行っていただく場合もあります。
原因となる病気が特定できる場合は、それぞれの病気に対する治療が最優先となります。病気が重篤な場合は、当院と連携する高度医療施設を紹介し、入院にて治療を行っていただく場合もあります。
原因となる病気がはっきりしないものや、あきらかに生活習慣によるものは、経過観察を行いながら栄養指導や運動指導などを行っていくこともあります。
その際、胃腸の粘膜修復薬、胃酸分泌抑制薬、胃腸の運動機能改善薬等を処方することもあります。
それ以外の生活習慣の改善として、以下のような試みが有効になる場合もあります。
- 3度の食事にこだわらず、少量ずつ数回に分けて食べる
- 早食い予防として、食事そのものを介助してもらう
- 刺激の少ない食事のため、出汁やハーブなどの香り付けをしてみる
- 食間にカロリー補充のサプリを摂取する
など