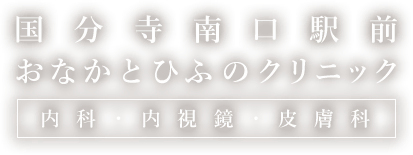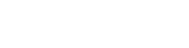ピロリ菌とは
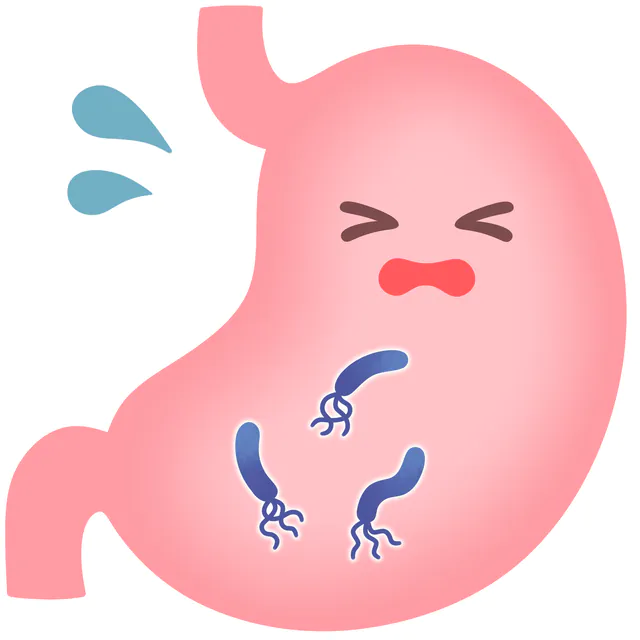 ピロリ菌は正式にはヘリコバクター・ピロリ(Helicobacter pylori)と呼ばれる細菌の一種です。強い酸性の胃液に満たされている胃の中で、ウレアーゼという酵素を出して胃内にある尿酸からアンモニアを作り出して胃酸を中和するバリアを作り、胃粘膜に定着します。
ピロリ菌は正式にはヘリコバクター・ピロリ(Helicobacter pylori)と呼ばれる細菌の一種です。強い酸性の胃液に満たされている胃の中で、ウレアーゼという酵素を出して胃内にある尿酸からアンモニアを作り出して胃酸を中和するバリアを作り、胃粘膜に定着します。
アンモニアには毒素があり、胃粘膜の防御能力を弱めることで、炎症やびらん、潰瘍などが起こり、慢性胃炎、萎縮性胃炎などを発症します。さらに、胃がん発症のリスクを高めます。また、胃粘膜の防御能力を弱めることで、胃・十二指腸潰瘍などの発症原因ともなることが知られています。感染が確認されたら、除菌治療を行い定期的に胃カメラ検査で経過観察することが大切です。
ピロリ菌の感染原因
ピロリ菌は、人間に感染する他、サルやネコなどの哺乳類の胃に生息することができます。感染経路は、食べ物や唾液などからの経口感染です。過去には、保菌動物の糞便などが混じった水や井戸水から感染することが一般的でしたが、日本を含む先進国では、水に関する衛生環境が整ってきたことで、箸や食器などの共有、離乳食を口移しで与える習慣、ペットの糞便などの不始末等が主な感染経路となりました。また、幼児期の感染が最も多いと考えられています。
これらの衛生環境に加えて、飲酒や喫煙、NSAIDsと呼ばれる抗炎症薬の常用、ストレスなどの生活習慣要因も、ピロリ菌感染のリスクが高まることがわかっており、若い世代では感染者が減ってきていますが、注意が必要です。
ピロリ菌に感染していると、胃の不調ばかりではなく様々な病気のリスクが増します。そのため、一度感染していないか検査を受けておくことをお勧めしています。
ピロリ菌の症状
ピロリ菌に感染しているだけでは、ほとんど自覚症状はあらわれません。しかし、感染によって胃内の環境が変わってくることで、以下のような症状があらわれることもあります。
- 胃痛
- 胃の不快感
- 腹痛
- 腹部膨満感
- 吐き気・嘔吐する
- 食欲不振になる
- 食後の胃もたれ
- 胸やけ
- 逆流性食道炎
- 貧血
- 体重減少
など
また、ピロリ菌によって慢性胃炎、萎縮性胃炎などを発症し、胃がんへ移行したり、胃酸の防御機能が障害されて、胃・十二指腸潰瘍を発症したりすることがあります。これらに加えて、貧血、下血、吐血、体重減少といった症状があらわれることもあります。
ピロリ菌の検査
胃カメラ検査を使用しない検査
尿素呼気試験
ピロリ菌は、ウレアーゼを使って尿素をアンモニアと二酸化炭素に分解します。
生成された二酸化炭素は、すぐに吸収され肺から呼気に混じって排出されます。
尿素呼気試験は、ピロリ菌の原理を利用します。
検査薬(13C-尿素)を服用し、服用前後の呼気に含まれた炭素の有無を確認します
胃酸分泌抑制薬を日頃から飲まれている方は、ピロリ菌に感染していても検査結果が偽陰性となる可能性がありますので注意が必要です。
抗体測定(血液検査)
ピロリ菌感染によって作られる抗体が、血液中に含まれているかを判定する検査です。
ただし、過去に感染していたが現在は除菌されている場合でも陽性になります。また、ピロリ菌に感染していなくても陽性となる擬陽性の可能性もあり、確定診断とはなりません。
糞便中抗体測定
ピロリ菌の一部は便中に含まれて排泄されます。
検便検査によって、ピロリ菌が便中に含まれるかどうかを判定するのがこの検査で、精度は高い検査とされています。
胃カメラ検査を使用した検査
胃カメラ検査によって胃粘膜のサンプルを採取し、試薬などを使った検査を行うことでピロリ菌感染の有無が分かります。
迅速ウレアーゼ試験
胃カメラ検査で粘膜の一部を採取し、尿素とリトマス試験紙のようなpH値で色が変わる試薬の入った器具で培養します。
ピロリ菌の出すウレアーゼが含まれていれば試薬の色が変化します。
組織鏡検法
採取した胃粘膜を特殊な色素で染色し、顕微鏡で観察することでピロリ菌の有無がわかります。
培養法
採取した胃粘膜を、37℃の環境で1週間程度専用の培地で培養します。ピロリ菌が増殖すれば陽性となります。最も正確な検査ですが、結果判明までに時間がかかることがデメリットでもあります。
ピロリ菌の除菌方法
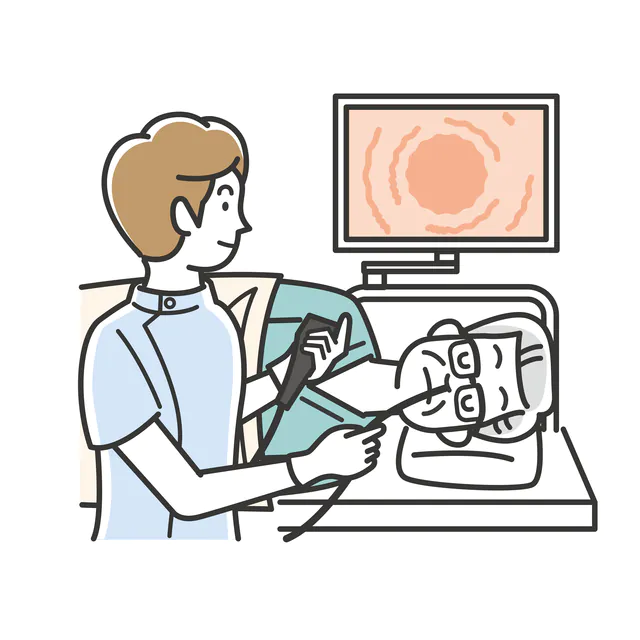 ピロリ菌感染が判明した場合は除菌治療を行います。胃潰瘍などで症状が激しい時期には除菌治療を行うことができませんので、まず潰瘍の治療を行い症状が落ちついたところで除菌となります。
ピロリ菌感染が判明した場合は除菌治療を行います。胃潰瘍などで症状が激しい時期には除菌治療を行うことができませんので、まず潰瘍の治療を行い症状が落ちついたところで除菌となります。
除菌治療は、2種類の抗生剤(抗菌薬)と1種類の胃酸分泌抑制薬(PPIまたはP-CAB)をセットで1日2回、1週間服用する薬物療法で行います。
1回目の治療が終わって、1ヶ月以上の期間をおいて除菌判定を行い、陰性であれば治療完了となります。
抗生剤への耐性菌が存在するため、1回目の治療成功率は70~80%程度となっており、除菌に失敗した場合は抗生剤の1種類を別のものにかえて同様の治療を1週間行います。除菌が成功するまで治療を続けることができますが、健康保険適用となるのは2回目の除菌治療までです。3回目以降は自由診療となります。
ピロリ菌除菌に成功すると、再感染の確率はほとんど無いと考えられています。慢性胃炎が解消されることで、胃・十二指腸潰瘍の発症数も大きく下がり、また胃がんの予防ともなります。
しかし、慢性胃炎で萎縮してしまった胃粘膜が元に戻ることはないため、ピロリ菌が陰性になれば胃がんの確率は大幅に減りますが、既に萎縮してしまった胃粘膜からの発がんリスクはありますので定期健診は必ず受けるようにしましょう。
ピロリ菌と胃がんの関係について
胃にピロリ菌が棲みつくと、ピロリ菌が産生する毒素や胃内の環境変化などによって胃粘膜は大きく傷つき、粘膜の萎縮などを引き起こします。
それによって、胃がんの発症確率が大きく高まります。WHO(世界保健機構)は、胃がんの80%はピロリ菌によるものとしていますが、日本ではさらに高く90%以上となっています。
もちろん、ピロリ菌に感染しているからといって、100%の人が胃がんになるわけではありませんが、大きくリスクが高まることは事実です。
そのため、ピロリ菌感染検査を行っていない方は、1度は感染検査を行い、陽性であれば除菌治療を行いましょう。除菌に成功しても定期健診をきちんと受け続けることが大切です。
ピロリ菌は除菌しないほうがいい?
 ピロリ菌は除菌した方がよいです。 最大の理由は、胃がんや胃・十二指腸潰瘍など、重篤な疾患のリスクを下げられることです。 胃がん患者のほとんどがピロリ菌に感染しており、除菌によりまた、除菌することで胃・十二指腸潰瘍の再発も抑えられるため、胃の健康を長期的に維持することで大きなメリットがあります。
ピロリ菌は除菌した方がよいです。 最大の理由は、胃がんや胃・十二指腸潰瘍など、重篤な疾患のリスクを下げられることです。 胃がん患者のほとんどがピロリ菌に感染しており、除菌によりまた、除菌することで胃・十二指腸潰瘍の再発も抑えられるため、胃の健康を長期的に維持することで大きなメリットがあります。
一方、除菌のデメリットとしては逆流性食道炎のリスクがわずかに高まる可能性があります。 ピロリ菌を除菌すると、胃が健康になり、胃酸分泌が相対的に増加することで、食道に胃酸が逆流する症状ただし、これは全ての人に起こるわけではなく、発症しても胃酸を中心とした症状を管理できます。
ピロリ菌の除菌を行うことで、がんリスクがゼロになるわけではありません。 定期的に胃カメラ検査を受け、早期発見を心がけることが重要です。 ピロリ菌の除菌と継続的な検査の両方で、胃がんのリスクに備えましょう。