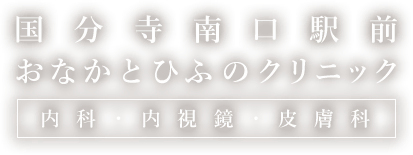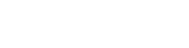過敏性腸症候群(IBS)とは
腹痛を伴う下痢や便秘、または下痢と便秘の繰り返し、おなかの異常な張りなどの便通異常の症状が長期間続いているのに、検査を受けても原因が見当たらない場合は、過敏性腸症候群を疑います。英語名のIrritable Bowel Syndromeの頭文字をとってIBSと呼ばれることもあります。過敏性腸症候群には4つの型があります。そのうち、下痢型は男性に、便秘型は女性に多い傾向があります。全体としては女性に多くみられます。生命に関わるほどの重篤な病気ではありませんが、日常生活に影響を及ぼす場合もあります。
過敏性腸症候群は何人に1人?
日本では10人に1人程度と、それほど珍しい病気ではありません。
比較的新しい病気の分類ですが、近年増加傾向にあります。
過敏性腸症候群の原因
この病気の原因は詳しく分かっていません。大腸は、小腸で栄養を吸収された消化物から、残った栄養素と水分を吸収しながら便を作る働きをしています。また、脳と密接に連絡を取りながら、便を肛門へ送る蠕動運動の運動機能と、便意を感じたり異常を感じたりするような知覚機能によって正常に働いています。
ところが、何らかのきっかけでこの機能に障害が生じると、知覚機能の異常によって腹痛を生じ、運動機能が異常に亢進や低下することで下痢や便秘が起こります。そのきっかけとして、生活習慣やストレスなどによる自律神経の乱れや、細菌やウイルス感染による腸炎の刺激があるのではないかと考えられています。
過敏性腸症候群はストレス・自律神経が原因?
 蠕動運動などの運動機能は腸を構成する平滑筋によって起こります。平滑筋は自律神経に支配されているため、自律神経のバランスが崩れることよって、腸の運動機能も乱れることになります。一方で、食べ物の種類、食べ方などによって腸の知覚機能が過敏になってしまうこともあります。
蠕動運動などの運動機能は腸を構成する平滑筋によって起こります。平滑筋は自律神経に支配されているため、自律神経のバランスが崩れることよって、腸の運動機能も乱れることになります。一方で、食べ物の種類、食べ方などによって腸の知覚機能が過敏になってしまうこともあります。
さらに、細菌・ウイルスなどの感染症をきっかけで発症する場合もあります。
過敏性腸症候群になりやすい人
腸の機能障害を起こす原因はまだはっきりとは分かっていませんが、前述の通りストレスなどによる運動機能障害、食習慣による知覚機能が過敏になるといった原因を考えると、ストレスを溜め込みやすい方や、なんでもご自身で背負い込みがちな方、食生活を中心として生活習慣が乱れがちな方がこの病気に至りやすいと考えます。年齢層で言うと、20~40歳代と比較的若い世代に多いです。また、若いうちは女性に多く、中高年になると男性に多くなってくる傾向があります。
過敏性腸症候群の便通異常のタイプ
過敏性腸症候群は、機能性ディスペプシアなどと共に機能性胃腸障害の一種に数えられ、国際的な消化器病学会のRome部会によって、詳細なガイドラインが設定されています。
このガイドラインの第4版であるRome4診断基準によると、うんちの特徴で以下の4つの型に分けられています。
| タイプ | 便形状・特徴 |
|---|---|
| 便秘型(IBS-C) |
硬便または兎糞状便が25%以上あり、軟便(泥状便)または水様便が25%未満のもの |
| 下痢型(IBS-D) |
軟便(泥状便)または水様便が25%以上あり、硬便または兎糞状便が25%未満のもの |
| 混合型(IBS-M) |
硬便または兎糞状便が25%以上あり、軟便(泥状便)または水様便も25%以上のもの |
| 分類不能型(IBS-U) |
便性状異常の基準がIBS-C,D,Mのいずれも満たさないもの |
過敏性腸症候群の診断
過敏性腸症候群の診断は、国際的な消化器病学会による診断基準に従って行います。診断基準は、2016年に定められたRome4規準を用いて行います。
もし、過敏性腸症候群が疑われる場合は、まずは潰瘍や炎症、がんといった器質的な病気や、甲状腺や副腎などの内分泌的な異常が無いという除外診断が必要です。感染症の有無を確認するために便検査を、他の器質的な病気の有無を確認するために血液検査や腹部超音波検査、大腸カメラ検査などを行う必要があります。
また、問診票にて、患者様の消化器症状、生活習慣、ストレスなどの精神的状況をご記入いただき、各種検査の結果と総合して診断を行っていきます。
その後、まずは薬物療法等を試みた後、十分な効果が得られない場合にはさらに専門的な検査を行うこともあります。
過敏性腸症候群の診断基準(Rome4基準)
以下の3つの項目のうち2つ以上の排便異常が、最近3ヶ月の間に平均して週1日以上あり、診断を受ける6ヶ月以上前からあらわれていること。
- 排便に関係した症状がある
- 排便の頻度(増える、減る)の変化を伴っている
- 便の外観(便形状)の変化を伴っている
※これらの症状があらわれており、胃・大腸カメラ検査や血液検査などで器質的、内分泌的な病気が認められない場合、過敏性腸症候群と診断できます。
過敏性腸症候群の治療(治し方)
過敏性腸症候群の発症や増悪には、食生活をはじめとする生活習慣が大きく関係していることが分かっています。そのため、治療は食事や生活習慣の見直しから始めます。食生活では、暴飲暴食、寝る前の食事などを避け、偏りの無い栄養素を含んだ食事内容に気をつけ、3食を規則正しい時刻で摂るようにします。お酒を飲みすぎることや、脂っこいものに偏った食事、香辛料の強い激辛の食事などは避けましょう。
また、規則正しい時間に入眠・起床する習慣をつけること、ストレスを運動や趣味などによってできるだけ発散することを心がけます。
これらの工夫をしても状態が改善されてこない場合は、便秘型、下痢型など、患者様それぞれの病態にあわせて薬物療法を行っていきます。
薬物療法以外の治療は?
 上記の通り、まずは生活習慣を改善することが大切です。そのためには食事療法や積極的な運動療法を中心に行っていきます。
上記の通り、まずは生活習慣を改善することが大切です。そのためには食事療法や積極的な運動療法を中心に行っていきます。
高脂質食、炭水化物を摂取しすぎるといった食事内容やアルコール、カフェイン、香辛料といった刺激物はこの病気の発症、増悪要因になります。これらの摂取を控えながら、バランスを考えた食事を摂っていくことが大切です。
積極的に摂取すると良い食品として、腸内細菌を整えるヨーグルト、味噌、納豆などの発酵食品が挙げられます。ただし、発酵食品は、人によっては便通異常を招くこともありますので、急に大量に摂り過ぎないようにしましょう。
一方、運動療法では激しい運動を行う必要はありません。それどころか疲労が溜まってストレスをかえって増大してしまうこともあります。適度なウォーキング、ジョギング、ゆっくりとマイペースで泳ぐスイミングなどの有酸素運動が有効です。なかでもウォーキングは、全身運動でありながら特別な準備も必要ありませんのでお勧めです。
また、ストレスの強い場合は、趣味や軽い運動、入浴、ストレッチなどの自分なりに解消できる方法を作っておくのがお勧めです。ご自身での解決が難しいような場合は、カウンセリングなどを受けてみるのも良いでしょう。
過敏性腸症候群の治療での注意点
過敏性腸症候群は、一般的に20~40歳代がピークとなる比較的若い世代に多い病気です。この病気は、加齢と共に発症や再発が減っていき、50歳を過ぎると特に罹患率は減少するという報告があります。また、加齢と共に便通異常の症状が、便秘型から下痢型へ、下痢型から便秘型へなどと変化しやすいこともわかっています。一方、過敏性腸症候群を発症した人は、同類の機能性胃腸障害に分類される機能性ディスペプシアや非びらん性胃食道逆流症などを合併しやすいことも分かっています。
受験ストレスによる過敏性腸症候群
 近年、受験シーズンになると、下痢や便秘などの排便障害を訴えて来院する大学受験生が増加してきています。
近年、受験シーズンになると、下痢や便秘などの排便障害を訴えて来院する大学受験生が増加してきています。
これは、受験のストレスや受験勉強の不規則な生活などによって自律神経が乱れ、胃腸症状となってあらわれているものと考えられます。
その中には、胃腸炎などの器質的な障害が見つからない方も多く、過敏性腸症候群の可能性が高い患者様も見受けられます。
大切な時期ではありますが、健康を損ねては本末転倒です。十分に生活習慣に気を配ってください。
「受験上の配慮」の利用
障害のある方、病気のある方などが大学入試などで受験する際に、様々な配慮を受けることができる「受験上の配慮」という制度があります。この中の「病弱」という該当理由に、過敏性腸症候群は当てはまります。そのため、当院では、過敏性腸症候群で苦しむ受験生の方には、積極的にこの制度を利用するようお勧めしています。
この制度の利用には、医師の診断書などが必要となりますが、当院でも診断書の発行、申請の方法などについてもご案内しています。
「受験上の配慮」の制度を利用することで、個室での受験や、テスト中でもトイレに行きやすい出入り口付近の席の用意などの配慮を受けることが可能になります。
近年では、この制度を利用できる学校が増えてきていますので、大学入試センターや各大学のWEBサイトなどでご確認ください。
また、制度をご希望の方は、いつでも当院までお問い合わせください。