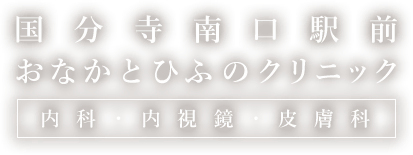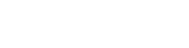当院の一般内科
 一般内科では、咳・鼻水など風邪のような症状や腹痛といった急性疾患から、生活習慣病のコントロールなどの他、体調が悪いがどこが悪いのか分からないといった場合に気軽に相談できる窓口としての役割まで、日常生活で良くある体調不良や病気などを診療しています。
一般内科では、咳・鼻水など風邪のような症状や腹痛といった急性疾患から、生活習慣病のコントロールなどの他、体調が悪いがどこが悪いのか分からないといった場合に気軽に相談できる窓口としての役割まで、日常生活で良くある体調不良や病気などを診療しています。
特に当院の院長は日本内科学会の総合内科専門医に認定されており、呼吸器、消化器、循環器、腎臓などの病気、内分泌の病気など幅広く対応しております。
以下のような症状でお困りの場合は、いつでも当院までご相談ください。
一般内科でよくある症状
一般内科でよくある病気
風邪
風邪は、鼻からのどにかけての感染性の上気道炎症の総称で、80~90%はウイルスによるもの、残りが細菌感染によるものと考えられています。ウイルスによる感染が原因の場合、有効な抗ウイルス薬が無いことが多いため、対症療法的に症状にあわせた薬物療法を行いながら、安静を保ち、栄養・水分補給を心がけて自然に治癒するのを待ちます。
一方、扁桃炎、副鼻腔炎、咽頭炎などで細菌感染が疑われるようなケースでは、抗生剤などの抗菌薬を処方することもあります。
風邪と油断していてこじらせてしまうと、気管支炎や肺炎に移行したり、稀にですが髄膜炎を起こしたりすることもあり、医師の判断が出るまで慎重に治療を続けるようにしましょう。
インフルエンザ
 インフルエンザは、インフルエンザウイルスによる感染症です。日本では、毎年12月から3月ごろまでが流行の時期で、総人口の8%程度が毎年罹患していると考えられています。
インフルエンザは、インフルエンザウイルスによる感染症です。日本では、毎年12月から3月ごろまでが流行の時期で、総人口の8%程度が毎年罹患していると考えられています。
風邪のような上気道症状(鼻水、咳、咽頭痛など)もありますが、高熱、全身倦怠感、関節・筋肉痛といった全身症状が強くあらわれる傾向があり、高齢者などが重症化すると重い肺炎やインフルエンザ脳症を合併することもあります。
近年では、インフルエンザウイルスに有効な抗ウイルス薬も開発されていますが、一番は「移らない、移さない」が大切です。そのためにも、毎年実施されている予防接種を受けておくことをお勧めします。
急性胃腸炎・感染性腸炎
急性胃腸炎は、主にウイルス感染によって胃腸に炎症が起こっている状態です。原因としては、ノロウイルス、アデノウイルス、ロタウイルスなどが一般的ですが、その他には、カンピロバクター、サルモネラ菌、O157に代表される腸管出血性大腸菌などの細菌感染、ストレスや薬の副作用によるものなどが挙げられます。
主な症状としては、腹痛、下痢、嘔吐で、その他にも発熱などの全身症状があらわれることもあります。ウイルス性の場合は、対症療法によって症状を抑え、下痢や嘔吐による脱水を防ぐ治療を行います。細菌性の場合は、抗菌薬を使用ことがあります。また薬物性の場合は、原因薬物の休薬や代替薬などを検討します。
急性胃腸炎で怖いのは脱水で、水分補給には十分な注意を払う必要があります。重症の場合は、入院の上で点滴による水分補給を行うこともありますが、一般的には経口補水療法(Oral Rehydration Therapy=ORT)が有効です。
気管支喘息・咳喘息
 気管支喘息は、なんらかの原因によって慢性的に炎症が続いていることで、気道が過敏になり、少しの刺激で急激に気管支が狭くなって、呼吸が苦しくなる喘息発作を起こす病気です。日本では近年増加傾向にあります。喘息発作は、夜間や早朝などに起こりやすく、症状としては、発作性の咳や痰のからみなどで、喘鳴と呼ばれるヒューヒュー・ゼーゼーという呼吸音が特徴的です。
気管支喘息は、なんらかの原因によって慢性的に炎症が続いていることで、気道が過敏になり、少しの刺激で急激に気管支が狭くなって、呼吸が苦しくなる喘息発作を起こす病気です。日本では近年増加傾向にあります。喘息発作は、夜間や早朝などに起こりやすく、症状としては、発作性の咳や痰のからみなどで、喘鳴と呼ばれるヒューヒュー・ゼーゼーという呼吸音が特徴的です。
喘息の治療は、発作が起きたときの適切な対応と、平常時はできるだけ発作が起こらないようにすることが大切です。そのため、発作対応の吸入薬や気道の炎症を鎮めるステロイドによる薬物療法などを適切に続けて行く必要があります。発作が出にくくなったからといって自己判断で治療を中止すると、慢性化や重症化して気道の状態が元に戻らなくなるリモデリングが起こることもありますので、医師の指導に従って根気よく治療を続けてください。
なお、咳喘息はアレルギーなどによって気道が過敏になり、咳だけが続く病気です。気管支喘息とは異なり、喘息発作や喘鳴などは伴いません。
頭痛
頭痛には、原因疾患があって起こる2次性のものと、原因疾患の無い1次性のものがあります。そのうちの多くは1次性の頭痛で、さらに緊張型頭痛、片頭痛、群発頭痛などに分類されます。頭痛が持病的に繰り返し起こる「頭痛持ち」の方は、この1次性頭痛の可能性が高いですが、原因疾患が隠れていないかどうかを、CTやMRIなどで精密検査を行う場合があります。その場合、連携する高度医療施設で検査を受けていただきます。その結果により治療方針を相談していきます。
また、今までにないような激しい痛み、どんどん悪化する頭痛、片側麻痺、しびれ、言葉が出にくいなどの症状がある場合は、脳血管障害や脳腫瘍などの急激な悪化の恐れがあります。その場合は、神経内科や脳外科などのある医療機関を受診するようにしてください。
胸の痛み
胸の痛みは、単におなかの張りやストレスなどで起こるものから、狭心症や心筋梗塞といった冠動脈障害、COPD、大動脈解離、肺塞栓症、がんに由来するものなどの重篤な病気まで、様々な原因が考えられるため、慎重に見極めることが大切になります。
そのため、血液検査、胸部超音波検査、心電図検査などの幅広い検査によって、原因を突き止め治療計画を立てていきます。心筋梗塞など重篤な病気の場合、連携する高度医療施設を紹介して、スムーズに治療を受けていただけるようにしています。
また、今までにないような激しい痛み、どんどん悪化する痛みや呼吸困難感などの症状がある場合は、大動脈解離脳や肺塞栓などの恐れがあります。その場合は、循環器内科や心臓外科などのある医療機関を受診するようにしてください。
花粉症
花粉症は季節性アレルギー性疾患の代表的なもので、花粉症の7割を占めるという春先のスギ花粉を筆頭に、晩秋まで様々な花粉が飛来し、そのためにアレルギー症状を起こす方は日本では4人に1人にも上るとされています。症状はくしゃみ、鼻水、鼻づまりといった鼻炎症状、目のかゆみなどの眼科症状などが代表的です。アレルギーを抑える抗アレルギー薬やかゆみを抑える抗ヒスタミン薬などの内服、点鼻、点眼が治療の中心となります。
スギ花粉に関しては根治治療となる舌下免疫療法が開発されていますが、現在のところ当院では取り扱っておりません。
貧血
酸素は、血液中の赤血球に含まれるヘモグロビンと結びついて、身体の隅々の細胞に届けられています。なんらかの原因により赤血球が減ることで、この細胞への酸素供給がうまく働かなくなってしまうのが貧血です。貧血には、鉄分の供給が足りず赤血球の生産が間に合わないもの(栄養不良、吸収障害など)や、月経や外傷などによる失血から血液そのものが不足するもの(他、消化管出血など)、なんらかの病気によって血液や赤血球が体内で消費や破壊されて不足するもの(慢性炎症、がんなど)、赤血球の工場である骨髄や製造に必要なたんぱく質の不調によって赤血球がうまく作られないもの(白血病、骨髄異形成症候群など)、といくつかの種類に分類されています。
貧血の主な症状は、息切れ、動悸、めまい、頭痛などが挙げられますが、一番多い原因であるヘモグロビンの原料となる鉄分が不足している場合、爪が割れやすい、皮膚のトラブル、頭髪のトラブルなどが起こる可能性もあります。原因を突き止めるためにも、血液検査や各種画像検査などを行い、適切な治療を行っていきます。
高血圧症
血圧とは、心臓が血液を送り出す際に、血管に与える圧力のことです。血圧が、常に高い状態が続いていると、血管壁に大きな負担がかかり、動脈硬化などを起こしやすくなります。動脈硬化が進行すると、脳梗塞などの脳血管障害、心筋梗塞などの冠動脈障害など、生命に関わる重篤な病気を合併しやすくなります。そのため、生活習慣の改善などによって、血圧を正常範囲にコントロールしておくことが大切です。生活習慣の改善だけでコントロールできない場合は、薬物療法を行うこともあります。
高血圧だけではほとんど自覚症状がありませんが、稀に頭痛、肩こり、耳鳴りなどを自覚することがあります。その場合は、冠動脈障害や脳血管障害を発症している可能性もあるかもしれませんので注意が必要になります。
糖尿病、高脂血症が合併している場合は、冠動脈障害や脳血管障害の発症リスクが高まるため、早期の治療介入をお勧めいたします。
糖尿病
糖尿病とは、細胞のエネルギー源である糖分の調整がうまくできず、常にブドウ糖が血中にあふれて、血糖値が高くなっている状態のことです。血糖値の高い状態が続くと、余剰な糖により体中の様々な細胞が障害される(糖毒性)のため、多様な合併症を発症する可能性があります。特に眼、腎臓、末梢神経の症状が出やすく、それぞれ進行すると失明、透析、下肢の壊死にまで発展してしまうため注意が必要です。
糖尿病の起こる原因は、ブドウ糖の代謝をコントロールするインスリンの異常によるものですが、インスリンが膵臓で産生されなくなる1型糖尿病とインスリンは産生されていてもうまく働けなくなる2型糖尿病に分類されています。そのうちのほとんどが、後者の2型糖尿病であり、生活習慣病に分類されています。
高血圧、高脂血症が合併している場合は、多様な合併症の発症リスクが高まるため、早期の治療介入をお勧めいたします。
高尿酸血症(痛風)
尿酸は、細胞が利用するプリン体の老廃物で、通常は身体に一定量貯蓄されますが、それ以上に量が増えると、尿に混ざって排泄される仕組みになっています。これがうまく働かなくなると、血液中に尿酸が溢れてしまい、結晶化します。尿酸の結晶は、非常にとがった形をしており、関節内に付着し蓄積すると、激しい痛みを伴う痛風発作を起こします。痛風発作はしばらくすると落ち着きますが、高尿酸血症状態を放置することで尿路結石や腎機能障害などを起こしやすくなります。そのため、しっかりと治療を続ける必要があります。
メタボリックシンドローム
 メタボリックシンドロームとは、内臓脂肪型肥満に加えて、高血圧症、脂質異常症(高脂血状態)、糖尿病のうちのどれか2つ以上が合併している場合のことを指します。それぞれの数値がそれほど重症化していなくても、動脈硬化による重篤な合併症を起こしやすいです。血圧、脂質、血糖値は高値になってもほとんど自覚症状があらわれず、突然重篤な状態があらわれる恐れがあります。条件に当てはまる方は、適切に対応しコントロールしていくことが大切です。
メタボリックシンドロームとは、内臓脂肪型肥満に加えて、高血圧症、脂質異常症(高脂血状態)、糖尿病のうちのどれか2つ以上が合併している場合のことを指します。それぞれの数値がそれほど重症化していなくても、動脈硬化による重篤な合併症を起こしやすいです。血圧、脂質、血糖値は高値になってもほとんど自覚症状があらわれず、突然重篤な状態があらわれる恐れがあります。条件に当てはまる方は、適切に対応しコントロールしていくことが大切です。
発熱外来
新型コロナウイルス感染症は、2023年5月からは5類感染症に変更されましたが、引き続き感染が拡がっては終息してといった状態です。
当院では、発熱外来を設けており、一般の患者様と接触がないよう、感染対策を行っております。
発熱のほかにも、咳や鼻水などの風邪につながる症状で受診される方も、発熱外来にて受診をお願いいたします。
発熱外来を受診すべきか迷った際には、お気軽にご連絡ください。