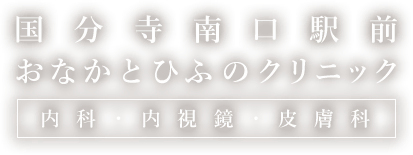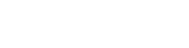当院の消化器内科
 消化器内科は食道から胃、小腸、大腸と繋がる消化管と、消化に関わる肝臓、胆嚢、膵臓の消化器全体の不調や病気を総合的に扱う診療科です。
消化器内科は食道から胃、小腸、大腸と繋がる消化管と、消化に関わる肝臓、胆嚢、膵臓の消化器全体の不調や病気を総合的に扱う診療科です。
当院では、腹痛、胸やけ、腹部膨満感、食欲不振、下痢・便秘などの症状でお悩みの場合や、症状ははっきりとあらわれていないものの、健康診断などで、潰瘍やポリープやピロリ菌感染などを指摘された場合に丁寧な問診で、隠れている病気の可能性などを判断します。それに応じて、血液検査、腹部超音波検査、胃カメラ・大腸カメラ検査などの適切な検査も行うことが可能です。
当院の医師は、日本消化器外科学会専門医であり、胃食道逆流症、胃炎(慢性・急性)、急性胃腸炎、機能性胃腸障害(機能性ディスペプシア、過敏性腸症候群など)、炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎やクローン病など)、その他各種消化器の病気について幅広く診察・治療に当たっております。おなかの不調については、当院までご相談ください。また、何科に相談すれば良いのか分からないような場合もお気軽にご質問ください。
診療案内
診療時間(消化器内科)
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日/祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30~12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ▲ |
| 14:00~18:00 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
▲:9:30~15:30
※受付開始・終了時間は、診療時間の30分前
日曜・祝日は消化器内科・肛門外科のみ診療(一般内科不可)
内視鏡検査
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日/祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30~18:00 | ● | ● | ● |
● | ● | ● | ▲ |
▲:9:30~18:00
※受付開始・終了時間は、診療時間の30分前
水曜日、第4土曜日は上部内視鏡検査(胃カメラ検査)のみ実施
外来担当(消化器内科)
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日/祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 院長 | 北村 | 北村 | 院長 | 北村 | 北村 | ▲ |
| 午後 | 院長 | 北村 | 北村 | 院長 | 北村 | - | - |
▲:日曜日(第2・4):院長
日曜日(第1・3・5):古川
内視鏡検査
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日/祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30~18:00 | 院長 | 院長 | 北村 | 院長 | 院長 | ■ | ▲ |
■:土曜日(第1・3・5):院長
土曜日(第2):沖
土曜日(第3):古川
土曜日(第4):北村
▲:日曜日(第2・4):院長
日曜日(第1・3・5):古川
消化器内科でよくある症状
消化器内科でよくある病気
(食道、胃、大腸)
食道
逆流性食道炎
 強い酸性の胃酸や消化酵素が混ざった胃の内容物が、食道に慢性的に逆流し続けるため、食道の粘膜が炎症を起こしてしまった状態です。従来は加齢性のものがほとんどでしたが、近年、食生活の欧米化によって若年層にも増えてきました。胃痛、胸やけ、げっぷ、呑酸、のどのつかえ、空咳などが主な症状で、生活習慣とも大きく関係があるとされています。
強い酸性の胃酸や消化酵素が混ざった胃の内容物が、食道に慢性的に逆流し続けるため、食道の粘膜が炎症を起こしてしまった状態です。従来は加齢性のものがほとんどでしたが、近年、食生活の欧米化によって若年層にも増えてきました。胃痛、胸やけ、げっぷ、呑酸、のどのつかえ、空咳などが主な症状で、生活習慣とも大きく関係があるとされています。
食道裂孔ヘルニア
横隔膜は胸腔と腹腔を隔てる薄い筋肉の膜です。その横隔膜にある食道を通すための隙間を食道裂孔と言います。
本来は食道とぴったりくっついていますが、なんらかの理由で締め付けが緩んで、胃が食道裂孔から胸腔へと飛び出してしまった状態を食道裂孔ヘルニアといいます。
食道裂孔ヘルニアは、逆流性食道炎を起こしやすくなることがわかっています。加齢による筋力低下、慢性的な咳による腹圧の上昇などが原因となります。
食道アカラシア
食道と胃の繋ぎ目は通常下部食道括約筋によってしっかりと閉じられており、食物が食道の蠕動運動によって口から胃に近づいてくると、その締め付けが緩み、食物を胃の中に送り込みます。この一連の運動がなんらかの原因でうまく働かなくなり、食物や飲料を飲み込むことができなくなるのが食道アカラシアです。
食べた物、飲んだものが食道内で詰まってしまうことにより、食道は拡張してしまい、胸痛、吐き気・嘔吐、背中の痛みなどがあらわれます。
軽度であれば薬物療法を行いますが、症状に応じて内視鏡による手術などを検討する場合もあります。
食道がん
 食道にできるがんで、早期にはあまり自覚症状がありませんが、進行すると咳、飲み込みにくさ、のどのつかえ、のどがしみるなどの症状があらわれます。
食道にできるがんで、早期にはあまり自覚症状がありませんが、進行すると咳、飲み込みにくさ、のどのつかえ、のどがしみるなどの症状があらわれます。
食道周辺には肺や心臓、それに伴う重要な血管などが密接しており、浸潤や転移を起こしやすいため、早期発見・早期治療の大切ながんの1つです。
危険因子としては、逆流性食道炎、飲酒、喫煙、熱いものをよく食べるなどが挙げられます。
特にお酒を飲んで顔が赤くなる方はアセトアルデヒドの分解が遅く、食道がんを起こしやすいと考えられていますので定期的な胃カメラ検査を受けるなど日ごろからの注意が必要です。
食道乳頭腫
食道にできる良性腫瘍で、はっきりとした原因は不明ですが生活習慣や、ヒトパピローマウイルス感染、逆流性食道炎などとの関連が指摘されています。
ほとんどの場合自覚症状は無く経過観察で良いのですが、嚥下に影響が出るような場合、内視鏡的な切除を検討することもあります。
食道バレット上皮
(バレット食道)
胃の粘膜は、円柱上皮という特殊な形をした粘膜構造によって胃液で溶かされることを防いでいます。
しかし、胃の内容物が慢性的に食道へ逆流し続けることで、通常は扁平上皮である食道粘膜が円柱上皮に置き換わってしまうことがあります。
この置き換わりが胃の入口から口方向へ3cm以上に拡がるとバレット食道といわれる状態になります。
バレット食道は食道がんの危険因子の1つで、バレット食道がんという特殊な形態のがんが発症しやすくなります。
そのため、バレット食道がみつかった場合は、定期的に胃カメラ検査で観察していくことが大切です。
食道カンジダ
(カンジダ性食道炎)
カンジダは、一般的に人の身体に見られる真菌(カビ)の1つです。通常食道で繁殖することはありませんが、なんらかの原因で抵抗力が弱った際に食道上に白い付着物となって繁殖することがあります。
抵抗力が戻ることで自然に治癒するため症状が軽ければ治療の必要はありませんが、重い症状があらわれている場合は抗真菌薬によって薬物療法を行います。
胃
胃潰瘍
 炎症などによって、皮膚や粘膜が上皮層より深く傷ついてえぐれている状態を潰瘍と言い、その状態が胃壁で起こっているものが胃潰瘍です。胃は粘膜層、粘膜下層、筋層、漿膜などと階層構造になっていますが、胃潰瘍は粘膜下層以下までえぐれてしまった状態となります。
炎症などによって、皮膚や粘膜が上皮層より深く傷ついてえぐれている状態を潰瘍と言い、その状態が胃壁で起こっているものが胃潰瘍です。胃は粘膜層、粘膜下層、筋層、漿膜などと階層構造になっていますが、胃潰瘍は粘膜下層以下までえぐれてしまった状態となります。
症状は、胃痛(みぞおちの痛み)、げっぷ、胃もたれ、吐き気、食欲減退などがあらわれ、進行すると粘膜下層以下の血管を傷つけて出血することがあります。
その場合、吐血や下血(真っ黒な便)などが見られるようになります。
原因の多くは、ピロリ菌感染によるものですが、その他にもストレスや飲酒などの生活習慣も影響します。重症化すると、胃に孔が開いてしまう胃穿孔を起こすことがありますので、早期発見・早期治療が大切です。
治療は主に、胃酸分泌抑制薬、粘膜修復薬などによる薬物治療となります。ピロリ菌検査が陽性の場合、症状が落ちついてからピロリ菌の除菌治療を行います。
また、胃がんが併存している場合がありますので、その後の経過観察が必要です。
慢性胃炎
胃粘膜に慢性的な炎症が起こっている状態が慢性胃炎です。ほとんどの場合、ピロリ菌感染による胃粘膜の変化が原因となっています。
一般的に、急性胃炎より自覚症状は軽めの傾向がありますが、胃もたれ、胃痛、膨満感などの症状が続くこともあります。この状態を放置してしまうと、徐々に胃の円柱上皮が修復できなくなり、ついにはその機能を失ってしまう萎縮性胃炎になる可能性があります。
ピロリ菌感染によって、胃がんのリスクは高くなりますが、萎縮性胃炎に進行するとさらにそのリスクは高くなります。治療は、胃酸分泌抑制薬、粘膜保護薬などの薬物療法を行い、症状が落ち着いたところでピロリ菌除菌治療を行います。
しかし、萎縮した粘膜が元に戻ることはありませんので、経過観察として、定期的に胃カメラ検査を受けていくことが胃がん予防のために大切です。
急性胃炎
急激に胃粘膜に炎症が起こり、激しい胃痛、吐き気・嘔吐などがあらわれます。
主な原因としては飲酒、ストレス、お薬の副作用、アレルギーなどが多く、時間の経過で自然に治癒することが多い病気です。
症状が重い場合には胃粘膜保護薬などの薬物治療を行います。
胃びらん
胃粘膜が炎症などによって浅く傷ついている状態が胃びらんで、びらん性胃炎とも言います。急性のものと慢性のものがあり、症状が強い場合は、胃粘膜保護薬・修復薬などの薬物療法を行います。稀に胃がんの初期症状として現れる場合があります。
萎縮性胃炎
萎縮性胃炎とは、胃に炎症が起こった状態が続き、胃液や胃酸を分泌する組織の減少が起こり、胃の粘膜が萎縮してしまう状態です。
主にピロリ菌感染によって発症し、ピロリ菌感染を放置すると萎縮の面積が徐々に増えていきます。
面積の増加に伴って胃がんのリスクも増加します。ピロリ菌除菌により萎縮性胃炎の進行を抑えることが可能です。
ピロリ菌
ピロリ菌は生水などを介して人に感染する細菌の一種で、正式にはヘリコバクター・ピロリと言います。ピロリ菌は、胃の内部で周辺にある尿素からアンモニアを作り出し、胃酸を中和するバリアを張って胃粘膜に棲みつきます。その毒素によって慢性的な炎症、潰瘍などが起こり、胃がんの原因にもなります。井戸水に生息していることが多く、井戸水を飲むことで感染すると言われています。現在、日本では飲み水の衛生環境は整っていますが、幼少期に親から子へ口移しで食物を与える習慣が残っており、それによって既に感染している親から子へピロリ菌が感染すると考えられています。除菌治療をしない限りは感染し続けますので、検査によってピロリ菌感染が判明した場合、除菌治療を受けることをお勧めしています。
胃がん
日本では、胃がんは長年に渡ってがんの種別でも上位を占めていたため、研究も進んでおり、治療法も確立されてきています。そのため、早期発見ができれば、侵襲の少ない胃カメラによる手術で完治できるようになってきています。ただし、早期には自覚症状が乏しいため、定期的な胃がん検査(特に胃カメラ検査)を受けておくことが大切です。
特に、日本では胃がんの9割以上がピロリ菌感染によるものと報告されており、ピロリ菌の除菌治療が大切です。
胃底腺ポリープ
胃底腺(いていせん)と呼ばれる組織にできる良性の腫瘍です。ピロリ菌に感染しておらず胃粘膜の萎縮などの変化がみられない健康な胃粘膜にできることが多く、悪性化の可能性は非常に低いと考えられています。胃酸分泌抑制の薬を長期内服することや、ピロリ菌除菌後しばらくすることで発症することもあります。
過形成性ポリープ
なんらかの刺激によって、胃粘膜が異常増殖して良性腫瘍化したものが胃過形成ポリープです。
ピロリ菌感染との関係性が非常に高く、除菌治療が成功すると、ポリープが小さくなったり消えてしまったりする例が多く見られます。
10mm以上に大きくなった場合や出血が見られる場合などは胃がん細胞が含まれている可能性があり、内視鏡的に切除することを検討します。
機能性ディスペプシア
胃痛、胃もたれ、げっぷや呑酸、胸やけ、少し食べただけでおなかがいっぱいになる早期飽満感など胃の不快な症状があります。検査をしても胃や食道などに炎症などの病変が見当たらない場合、この病気が疑われます。胃の運動機能や知覚機能が、ストレスや生活習慣などによって障害されてしまっている状態で、過敏性大腸炎などと同様に機能性胃腸障害に分類される病気です。生活習慣の改善の他、消化管の運動機能を改善する薬や胃酸分泌を抑制する薬などによる薬物療法を行うこともあります。潜在的なピロリ菌感染があれば除菌することで改善する場合があります。
アニサキス
 アニサキスは、貝類を除くほとんどの海洋魚介類を宿主とする寄生虫で、特にサバ、イワシなどの青魚やイカ類、サケ類に多いとされます。人間を宿主とすることはできませんが、生きているアニサキスを含む魚介類を生食、または加熱不足で摂取した場合、胃や腸壁にもぐりこもうとするアニサキスによって、激しい痛み、吐き気・嘔吐などの症状があらわれます。アニサキスが胃壁にとりついた場合は、早期に胃カメラで摘除することにより症状はすぐに治まりますが、現在のところアニサキスを死滅させる有効な内服薬はありません。
アニサキスは、貝類を除くほとんどの海洋魚介類を宿主とする寄生虫で、特にサバ、イワシなどの青魚やイカ類、サケ類に多いとされます。人間を宿主とすることはできませんが、生きているアニサキスを含む魚介類を生食、または加熱不足で摂取した場合、胃や腸壁にもぐりこもうとするアニサキスによって、激しい痛み、吐き気・嘔吐などの症状があらわれます。アニサキスが胃壁にとりついた場合は、早期に胃カメラで摘除することにより症状はすぐに治まりますが、現在のところアニサキスを死滅させる有効な内服薬はありません。
十二指腸潰瘍
十二指腸や十二指腸の胃に近い部分にできる潰瘍です。十二指腸では、通常は胆汁や膵液などの消化液によって中和される胃酸が、ピロリ菌感染によって中和できなくなり、粘膜を傷つけることなどから発症します。十二指腸の粘膜は比較的薄く、穿孔を起こしやすいため、早期治療が重要になります。治療は胃酸分泌抑制薬や粘膜保護薬などによる薬物療法を中心に行います。
大腸
急性胃腸炎、感染性腸炎、食中毒
主にウイルス感染(ノロウイルス、ロタウイルスなど)、細菌感染(サルモネラ菌、カンピロバクター、O157などの病原性大腸菌)によって起こる急性の胃腸炎で、腹痛、嘔吐、下痢などの他、発熱などの全身症状があらわれることもあります。
ウイルス感染の場合、有効な抗ウイルス薬が開発されていないこともあり、各種症状に対する対症療法と脱水予防などによって治療を行います。細菌感染の場合は抗菌薬などによる薬物療法を行います。
虫垂炎
 盲腸の先端に紐のように飛び出している虫垂に、糞便などが詰まることによって炎症を起こしてしまうのが虫垂炎です。一般的には盲腸と呼ばれることもあります。初期には、みぞおちのあたりの痛み・不快感が出現し、だんだん下に降りて行くことで右下腹部の痛みがあらわれます。近年では、抗菌薬の投与による治療が優先となりましたが、何度も虫垂炎を繰り返している場合や、腹膜まで炎症が起こるなど進行している場合には手術が必要となります。その場合、当院と連携する高度医療機関を紹介し、スムーズに治療を受けていただけるようにしております。
盲腸の先端に紐のように飛び出している虫垂に、糞便などが詰まることによって炎症を起こしてしまうのが虫垂炎です。一般的には盲腸と呼ばれることもあります。初期には、みぞおちのあたりの痛み・不快感が出現し、だんだん下に降りて行くことで右下腹部の痛みがあらわれます。近年では、抗菌薬の投与による治療が優先となりましたが、何度も虫垂炎を繰り返している場合や、腹膜まで炎症が起こるなど進行している場合には手術が必要となります。その場合、当院と連携する高度医療機関を紹介し、スムーズに治療を受けていただけるようにしております。
大腸ポリープ
 大腸にできる良性のできもので、腫瘍性のものと非腫瘍性のものがあります。そのうち腫瘍性の腺腫と呼ばれるポリープが最も多く見つかりますが、この腺腫は放置すると一定の確率でがん化することが知られており、そのため前がん病変と呼ばれています。
大腸にできる良性のできもので、腫瘍性のものと非腫瘍性のものがあります。そのうち腫瘍性の腺腫と呼ばれるポリープが最も多く見つかりますが、この腺腫は放置すると一定の確率でがん化することが知られており、そのため前がん病変と呼ばれています。
大腸にポリープができてもほとんど自覚症状があらわれることはありません。そのため、健康診断や大腸がん検診などで偶然発見されることが多くなっています。健康診断の便潜血検査や腹部画像検査などでポリープの疑いを指摘された方は、確定診断のため大腸カメラ検査を受けることをお勧めしています。当院でも大腸カメラ検査を行っており、ポリープがみつかった場合、その塲で入院無しに切除を行うことが可能です。ただし、ポリープが大きい場合や数が多い場合には、出血予防のため入院可能な施設を紹介させていただくこともあります。
大腸がん
日本では、食生活の変化とともに大腸がんが増加しており、2022年の最新データでは罹患者数が男女ともに2位、死亡者数は男性2位、女性1位となっています。しかし、早期のうちに発見できれば、大腸カメラによる簡単な切除で完治ができるがんの一種です。ただ、早期のうちは自覚症状が乏しいため、定期健診による便潜血検査や画像検査で異常が見つかった場合、大腸カメラ検査にて確定診断を行うことが大切です。また、40歳以上になると、前がん病変である腺腫が増えてくるため、定期的な大腸カメラ検査の受診が推奨されています。40歳に達していなくても、血縁者に大腸がんや大腸ポリープの既往症がある方は、お早めに定期大腸カメラ検査を受診するようにしましょう。
腸閉塞
イレウスとも呼ばれる腸閉塞は、薬剤などによる腸管の運動機能障害や手術、外傷などによる瘢痕の癒着などによって大腸に通過障害が起こっている状態で、完全に腸管が塞がってしまっているケースや腸管が狭窄しているだけのケースもあります。
症状としては吐き気・嘔吐、腹部膨満感、便秘、腹痛などですが、進行すると完全に便やガスが通過できなくなり、腸管が破れて腹膜炎を起こしたり、敗血症を起こしたりすることもありますので、症状の重い場合は緊急手術を検討することになります。
その場合、当院と連携する高度医療機関を紹介してスムーズに治療を受けていただけるようにしております。
大腸憩室
大腸の粘膜が、腸内圧力の増加などによって筋層に向けて小さな袋状にへこんでしまい、腸粘膜から見ると小さな孔(1~10mm程度)ができているように見える状態です。それ自体であれば、特に治療の必要はありませんが、便が孔に嵌まることで細菌感染を起こすこと(大腸憩室炎)や、出血を起こすこと(大腸憩室出血)もあり、経過観察が必要です。
大腸憩室炎
大腸にできた憩室内に便などが入り込み、細菌感染から炎症を起こしてしまった状態が大腸憩室炎です。激しい腹痛、発熱などがあらわれ、重症化すると腸に穴が開く(穿孔)こともあります。通常は抗菌薬などによる薬物療法を行いますが、重症化した際は手術が必要になることもあります。その場合、当院と連携する高度医療機関を紹介し、スムーズに治療を受けていただけるようにしております。
憩室出血
憩室の部分は腸壁が非常に薄くなっており、少しの刺激で出血を起こすことがあります。これが大腸憩室出血で、腹痛などを伴わない突然の血便が出現することが特徴です。特に、ワーファリンやリクシアナなどの抗凝固薬を服用している方に多いとされています。出血した場合は、絶食して腸管を安静に保つことや、大腸カメラによる止血処置などで対応しますが、何度も繰り返す場合や、出血の多い場合には手術を検討することもあります。その場合、当院と連携する高度医療機関を紹介し、スムーズに治療を受けていただけるようにしております。
虚血性腸炎
虚血性腸炎は、大腸への血流がなんらかの原因で一時的に途絶えて、腸粘膜への酸素・栄養供給が阻害されるために、大腸粘膜に急性の炎症が起こる病気で、虚血性大腸炎とも言います。突然腹痛があり、排便後に出血があり、時には便器が真っ赤になるほどの出血で緊急受診される方もいます。
多くの場合、絶食による腸管の安静によって数日で回復します。
痔
 痔は肛門のトラブルでは一番多い病気で、内痔核・外痔核(いぼ痔)、裂肛(切れ痔)、痔ろう(穴痔)の3種類に分けることができます。
痔は肛門のトラブルでは一番多い病気で、内痔核・外痔核(いぼ痔)、裂肛(切れ痔)、痔ろう(穴痔)の3種類に分けることができます。
痔ろうは手術による治療しかありませんが、その他の場合、薬物療法や生活習慣の改善で症状を軽減することができます。
当院でも痔疾治療を行っていますので、お早めにご相談ください。
潰瘍性大腸炎
直腸から始まり、進行すると大腸全域に渡って炎症が続き、潰瘍などを生じる病気です。後述のクローン病と似ており、炎症性腸疾患に分類されていますが、炎症が大腸に限られ連続的にあらわれることが特徴です。
発症の原因は今のところ不明ですが、自己免疫が関わっていると考えられています。また、確立された治療法が開発されておらず、国の指定難病となっています。症状が重くあらわれる活動期(再燃期)と症状が落ちついている寛解期を繰り返すのが特徴です。
活動期には腹痛や、粘血便を含む下痢と便秘の繰り返しなどの症状があらわれます。重症の場合は手術を検討することもあります。
現在は、活動期に効果的に症状を抑える薬などが開発されており、寛解期にも適切な薬物療法と生活習慣の改善を行うことで、ある程度の日常生活が送れるようになります。
クローン病
潰瘍性大腸炎と同様に、炎症性腸疾患に分類されています。活動期と寛解期を繰り返すなどの症状は似ていますが、潰瘍性大腸炎との違いは、口から肛門までのどこにでもあらわれる可能性があることや、潰瘍が重症化しやすいことなどが挙げられます。
クローン病も、明らかな原因や確立された治療法が無く、国の指定難病になっています。小腸と大腸との接合部あたりから、大腸の上行結腸のあたりまでに症状があらわれやすいのですが、目や口、肛門などにも炎症が起こる可能性があります。薬物療法、血球成分除去療法、栄養療法などの他、重症の場合は手術を検討することもあります。
過敏性腸症候群
下痢、便秘、下痢と便秘の繰り返し、腹部の異常な膨満などの症状があり、大腸カメラ検査などを行っても炎症や潰瘍などの器質的な病気や内分泌異常などが見当たらない場合、過敏性腸症候群が疑われます。
大腸の蠕動運動などの運動機能、痛覚や便意などの知覚機能になんらかの原因で異常が生じていることが原因と考えられており、機能性ディスペプシアなどと同時に機能性胃腸障害に分類されています。
発症の要因は生活習慣やストレスなどが大きくかかわっていると考えられており、生活習慣の改善や対症療法的な薬物療法などによって治療を行います。
便秘
腸の長さやその運動に個人差があるため、排便の習慣にも個人差があり、便秘の診断は難しいですが、一般的には3日以上排便が無い状態、または排便があっても満足感(快便感)を得られない状態を便秘と定義しています。腸に潰瘍やがんやポリープができることによって、物理的な狭窄が生じる器質性の便秘や、腸の運動機能の低下によるもの、便意に関する知覚機能の異常によるものなど、様々な種類があり、その原因や便秘が起こりやすい要因なども人によって異なります。
便秘は女性に多い病気で、排便に関することを人に相談するのが恥ずかしいなどの理由で放置してしまい、便秘の原因を悪化させている例も多く見られます。
当院では、消化器外科学会の専門医が、便秘に関するお悩みについても丁寧にお伺いしておりますの。恥ずかしがってかえって悪化させてしまうような事態に陥らないよう、お早めにご相談ください。