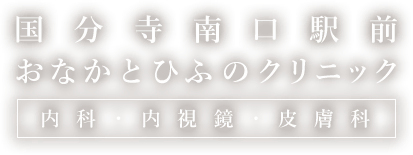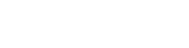その症状は本当に胃潰瘍?
 胃潰瘍は、以前はストレスが原因となって発症すると考えられ、胃痛、胸やけ、げっぷ、むかつきなど、患者様の訴える症状のみで診断してしまうこともありました。また、胃酸分泌抑制薬などの強力なお薬によって、容易に症状を軽減できるようになったため、薬物療法に頼ってしまいがちな傾向もあります。
胃潰瘍は、以前はストレスが原因となって発症すると考えられ、胃痛、胸やけ、げっぷ、むかつきなど、患者様の訴える症状のみで診断してしまうこともありました。また、胃酸分泌抑制薬などの強力なお薬によって、容易に症状を軽減できるようになったため、薬物療法に頼ってしまいがちな傾向もあります。
しかし、胃潰瘍を含む上部消化管の病気による症状は、どれも非常に似ています。そのため、軽度の胃潰瘍と診断され薬物療法によって症状を抑えていたが、数年後に精密検査をした際に、実は胃がんだったなどの症例もあります。
そのため、胃潰瘍の診断には胃カメラ検査が必須になってきています。これは、単に胃潰瘍であると判定するためだけではなく、胃がんなどの重篤な病気が隠れていないかを同時に判断していくための検査でもあります。
胃カメラ検査といえば、かつては辛く苦しい検査とされていましたが、医療機器の進歩や医療技術の発展によって、今ではほとんど苦痛を感じないようになってきています。
当院は胃カメラ検査を専門としており、経験豊富な医師が検査を担当しますので、安心してご相談いただけます。
胃潰瘍はどのようにして発症する?
胃は、食べた食物をドロドロに溶かすために、強い酸性の胃酸や消化酵素(ペプシンなど)を分泌しています。これらは、食物に含まれる栄養分を腸で吸収しやすいように働く作用でもありますが、胃の粘膜をも溶かしてしまおうとする攻撃力も持っています。
胃の粘膜は、円柱上皮という特殊な細胞でできており、その細胞から重炭酸塩やプロスタグランジンが含まれる粘液を分泌し、胃液の攻撃から溶かされてしまわないよう防御しています。健康な胃ではこのバランスが保たれていますが、何らかの障害が起こるとそのバランスが崩れて胃液の攻撃力が強くなり、胃粘膜が炎症を起こしてしまいます。胃壁は層構造になっており、大きく分けると内側から「粘膜層」「粘膜下層」「筋層」「漿膜下層」「漿膜」となります。
溶かされてしまった影響が、どの層に至っているかによって以下の表のように分類されています。
| 溶かされた状態 | 溶かされた程度 |
|---|---|
| びらん(糜爛) | 粘膜層にとどまっている |
| 潰瘍 | 粘膜層より深い粘膜下層以下に進行している |
| 穿孔性潰瘍 | 深く溶かされ消化管に穴が開いている |
胃潰瘍には、急性のものと慢性のものがあります。急性胃潰瘍は、激しいストレスや服用したお薬などの影響で急激に発症します。形の定まらない潰瘍やびらんがたくさんできることが特徴です。軽い症状であれば、経過観察で改善することが多いです。
一方、慢性胃潰瘍は、円形の潰瘍が少数できますが、潰瘍の程度が比較的深い傾向があり、治るまで少し時間がかかります。また何度も再発する傾向があることが特徴です。
胃潰瘍の原因と発症のトリガー
- ストレスなどの精神的要因
- 暴飲暴食、強い香辛料、刺激物などの大量摂取による物理的要因
- ヘリコバクター・ピロリ感染
- 抗炎症薬(NSAIDs)やステロイド薬の多用
- 血液をサラサラにする抗凝固薬の継続服用などによる副作用
- 内分泌疾患、内分泌腫瘍の存在
胃潰瘍の原因はストレスではない?
近年の研究によって、胃潰瘍の多くはピロリ菌感染によって、胃粘膜にダメージが及ぶことが原因であるとわかってきました。
また、NSAIDsと言われる抗炎症薬やステロイド薬の常用も原因の1つです。痛み物質であると同時に、消化管粘膜保護作用のあるプロスタグランジンの産生が抑えられることで、胃潰瘍を発症してしまうNSAIDs胃潰瘍も問題になっています。特に、抗血栓薬として少量用いられるアスピリン(NSAIDsの一種)の常用も問題となっています。
これらの原因に、ストレスなどの外的要因が加わることで発症のリスクが高まります。ストレスは、以前のように胃潰瘍の主な原因と考えられなくなっていますが、発症のきっかけとして胃潰瘍と関連があると言えます。
胃潰瘍のセルフチェック
さらに以下のような症状があらわれた場合、重症化している可能性があります。
- 下血した(黒色のタールのような便)
- 吐血した
胃潰瘍の症状について
前項のチェックリストと合わせて、以下の症状も参考にしてください。
胃潰瘍の自覚症状のあらわれ方は人によって異なります。初期には症状があらわれない患者様も多いのが特徴です。自覚症状があらわれる場合、みぞおちの辺り(心窩部)の痛みが一番に多く、その他に胸やけ、吐き気や嘔吐、食欲不振などがあらわれることもあります。
潰瘍が深くなると、胃壁の中の血管が傷ついて出血することがあります。その場合、吐血や下血となってあらわれます。血液は、胃酸と混じると黒く変色します。一般に黒色便と呼ばれる黒く、ドロッとしたタール状の便があらわれます。
胃潰瘍と十二指腸潰瘍の痛みの特徴
 胃潰瘍と十二指腸潰瘍では、様々な症状が共通しています。その中でも、みぞおちの痛み(心窩部痛)は最も一般的な症状です。この痛みが、どのようなタイミングであらわれるかによって、潰瘍の起こっている場所がある程度判断できます。
胃潰瘍と十二指腸潰瘍では、様々な症状が共通しています。その中でも、みぞおちの痛み(心窩部痛)は最も一般的な症状です。この痛みが、どのようなタイミングであらわれるかによって、潰瘍の起こっている場所がある程度判断できます。
胃潰瘍の場合、胃に食物が入ってから痛み始め、腸へと移動するまでの間にあらわれることが多いです。
これに対し十二指腸潰瘍は、胃に食物が無い状態や空腹時にあらわれることが多いです。そのため、早朝に痛みが出現し、目が覚めるなどということもあります。
しかし、どちらも重症になることで、いつでも痛みを生じることがあります。
また、まったく痛みを生じず、その他の症状と胃カメラ検査によって診断される方もいますので注意が必要です。
その他の軽症の場合でも生じる症状
 胸やけ、げっぷや呑酸、吐き気や嘔吐、胃もたれ、口臭、食欲不振、体重減少といった症状は、胃潰瘍発症の原因となるピロリ菌感染や、発症のきっかけとなるストレスなどの自律神経の乱れなどによって、胃酸の分泌が過多になってしまうことで起こります。
胸やけ、げっぷや呑酸、吐き気や嘔吐、胃もたれ、口臭、食欲不振、体重減少といった症状は、胃潰瘍発症の原因となるピロリ菌感染や、発症のきっかけとなるストレスなどの自律神経の乱れなどによって、胃酸の分泌が過多になってしまうことで起こります。
胃液には、強酸性の胃酸の他に、ペプシンと呼ばれる消化酵素が含まれています。ペプシンは、胃酸の影響を受けて食物を分解する能力が高まり、同時に様々な食物を溶かす働きがあります。胃の粘膜がこの胃液によって溶かされないのは、粘膜から分泌される粘液が胃粘膜全体を覆って防護しているためです。健康な胃ではこの攻撃と防護のバランスが保たれていますが、そのバランスが崩れることで胃粘膜は胃液によって障害され、炎症やびらん、潰瘍などが生じ、症状としてあらわれます。
ただし、胃潰瘍・十二指腸潰瘍などの他、胃炎、胃がん、逆流性食道炎といった他の病気にもこれらの症状は共通しています。胃がんなどの他の病気による症状の可能性もあるため、胃カメラ検査によって直接的に上部消化管の粘膜の状態を確認し、正しく判断することが大切になります。
背中の痛みについて
胃潰瘍では主にみぞおちの辺りが痛むことが多いですが、背中まで痛むこともあります。しかし、背中の痛みは、筋肉や脊椎など整形外科領域の障害によって発症することもあります。また、内科的な問題としては、胃、十二指腸などの消化管の他、膵臓などの消化器に関わるもの、心臓などの病気からあらわれるものもあります。
心臓などの場合、急激に生命に関わる事態が発生する可能性もあります。また、膵臓がんなどの重篤な病気の可能性もあるため、しっかりと見極めることが大切です。
正確に判断するためにも、胃カメラ検査、血液検査などの他、超音波検査などを行い、原因を特定していきます。
潰瘍が重症化した場合の下血
胃の粘膜層にはほぼ血管が通っていませんが、粘膜下層以下に潰瘍が生じた場合は、胃壁内を通っている血管が破れて出血を起こす恐れがあります。この時、出血した血液は小腸から大腸へと進み、便に混ざって肛門から排泄されます。これを下血と言い、食道から十二指腸などの上部小腸までのどこかで出血が起こり、便に混じって排泄されることを指します。
胃で出血が起こると、胃酸と混じることによって、血中のヘモグロビンが酸化して塩酸ヘマチンという物質に変わります。それによって色が真っ黒または暗紫色になります。また、消化もされにくく、黒くドロッとした状態で排泄されるため、黒色便またはタール便と呼ばれています。
潰瘍が重症化した場合の吐血
胃潰瘍で出血した場合、嘔吐と同時に血液を吐き出す吐血(とけつ)として症状が起こることがあります。口から血液を吐き出した場合、胃や食道など消化管からの出血は「吐血」と言い、肺や気管支など呼吸器系からの出血の場合を「喀血(かっけつ)」と言います。
みぞおちの痛み、げっぷ、胸やけなどの症状があって血を吐いた場合は、食道や胃からの出血による吐血が考えられます。少量の吐血の場合は、胃液が混じって下血と同様にヘモグロビンが酸化し、コーヒーを淹れた後の残りかすの様な色(濃褐色)となることが多いですが、大量出血の場合は鮮血色となります。どちらも、潰瘍が重症化しており、大量出血の場合は出血性ショックを起こすことなどもありますので、お早めにご相談ください。
特に、高齢者の場合は出血から脳梗塞や心筋梗塞が引き起こされる恐れもあり、注意が必要です。
胃潰瘍の検査・診断
 問診にてある程度の推測は可能ですが、実際に胃粘膜のどの部分がどの程度障害されているのか、潰瘍以外の病気の徴候は無いのかなどをしっかりと見分けることが大切です。そのために、超音波検査や血液検査などを行いますが、確定診断ができるのは胃カメラ検査です。医師が、食道、胃、十二指腸などの粘膜の状態を実際に目視で確認するため、正確に判断することが可能です。
問診にてある程度の推測は可能ですが、実際に胃粘膜のどの部分がどの程度障害されているのか、潰瘍以外の病気の徴候は無いのかなどをしっかりと見分けることが大切です。そのために、超音波検査や血液検査などを行いますが、確定診断ができるのは胃カメラ検査です。医師が、食道、胃、十二指腸などの粘膜の状態を実際に目視で確認するため、正確に判断することが可能です。
胃カメラ検査は、かつては辛い検査の代表的なものでしたが、検査装置や医師の検査技術の向上などが進み、現在ではほとんど苦痛を感じずに行うことも可能となりました。当院でも負担を最小限にした検査を実施していますので、安心してご相談ください。
なお、他院で生活習慣病などの治療をしており、当院で検査を希望される方にも対応しています。当院では、これまで診ていただいていた医療機関と連携をしながら、既存の医院で治療を継続するための情報提供にも対応しています。また、改めて当院で治療再開を希望される方にも対応しています。
胃潰瘍の治療
食事療法・食事制限
症状が強い間は、まずは胃酸の分泌を促さないよう食事制限をし、薬物療法を行います。その後、症状が治まってきたら、食事療法を行っていきます。
食事療法では、できるだけ柔らかく胃に負担をかけないものを、少量ずつ、回数を分けて摂るようにします。
欧米では胃潰瘍の際、胃酸の中和作用がある牛乳やバニラアイスなどを食べることを奨励することもあるそうです。
時間の経過によって症状が落ちついてきたら、定期的に通院し、徐々に普段の食事に戻して経過観察していきます。
なお、再発を防止するため、喫煙習慣のある方は禁煙してください。また、当面の間は飲酒やコーヒー、煎茶などカフェインの強いものは控えるようにしてください。
※喫煙は血管を収縮させ、胃の運動機能低下や胃酸分泌増加を促進します。再発を防止するためにも、必ず禁煙してください。
薬物療法
近年では、胃潰瘍はほとんどの場合、胃酸分泌抑制薬や胃粘膜修復・保護薬などを中心にした薬物療法を行います。
胃潰瘍の原因の多くはピロリ菌感染です。胃潰瘍の確定診断は胃カメラ検査で行うため、同時にピロリ菌感染検査も実施します。ピロリ菌陽性であれば、ある程度の症状が治まってから、時期を見て除菌治療を行います。ピロリ菌除菌を行わない場合、ピロリ菌が原因で胃潰瘍を発症した方の7割が1年以内に再発するという報告もあります。一方、除菌に成功した方の再発率は1~2割程度とされていますので、除菌は再発予防に重要です。
また、近年問題になっている抗炎症薬(NSAIDs)やステロイド薬などによる薬物性の胃潰瘍の場合、それらの薬剤を処方した医師と相談しながら、休薬、または代替薬との置き換えを検討することになります。これらの治療によって、2ヶ月程度で完治となることが一般的です。
内視鏡的治療
 吐血や下血、貧血症状などの出血にかかわる症状があらわれている場合は、止血処置をします。近年では、ほとんどがスコープについた処置用の器具によって止血を行います。ただし、穿孔を疑う症状があらわれている場合は、手術療法を行います。
吐血や下血、貧血症状などの出血にかかわる症状があらわれている場合は、止血処置をします。近年では、ほとんどがスコープについた処置用の器具によって止血を行います。ただし、穿孔を疑う症状があらわれている場合は、手術療法を行います。
その場合は、当院が連携している高度医療機関をご紹介しますのでご安心ください。
手術療法
激しい胃痛が肩などまで拡がり、患部の圧痛が強い、呼吸が荒くなる、激しい発汗などの症状があらわれる場合は、穿孔を疑います。穿孔は、胃カメラ検査で発見される場合もあり、緊急手術が必要となります。
この場合、当院と連携する高度医療機関をご紹介し、スムーズに手術を行うようにしています。
胃潰瘍かなと思ったら当院へご相談ください
 胃潰瘍かなと思っても、上部消化管の不調による症状はどれも共通するものが多いです。実際には、炎症だけで潰瘍には至っていなかった病気から、胃がんによる重篤な病気だったなど様々です。
胃潰瘍かなと思っても、上部消化管の不調による症状はどれも共通するものが多いです。実際には、炎症だけで潰瘍には至っていなかった病気から、胃がんによる重篤な病気だったなど様々です。
胃潰瘍と特定するためには、胃カメラ検査を行い確定診断となってから治療をすることが大切です。