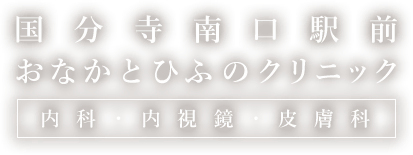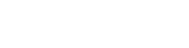おなかが張る感じ
 おなかが張っているという表現は、おなかに液体やガスなどが溜まって苦しい感じをあらわしており、医学的には腹部膨満感と言います。
おなかが張っているという表現は、おなかに液体やガスなどが溜まって苦しい感じをあらわしており、医学的には腹部膨満感と言います。
腹部膨満感は一般的に、胃の運動機能が低下するなどが原因で胃に食物が長く滞留してしまい、胃が重い感じやみぞおちのあたりが張っている感じがするなどの胃が張っている症状と、下腹にガスがたまっている感じや下腹がゴロゴロしている感じなどの腸が張っていたり過敏に動いていたりするような症状の2つに分けることができます。
腹部膨満感のメカニズム
ガスによる腹部膨満感のメカニズム
 胃や腸では消化の際に発酵や腐敗がすすみ、化学反応によってガスが生じます。こうした消化管内のガスの一部は、血液に混じって呼気や皮膚呼吸によって体外に排出され、それ以外のガスもげっぷやおならとなって体外に排出されます。しかし、様々な理由でガスが発生しすぎると吸収や排泄が遅くなり、ガスが消化管内に溜まりすぎて腸などが膨らんでしまい、周辺を圧迫することで腹部膨満感が生じます。こうした状態を鼓腸とも言います。
胃や腸では消化の際に発酵や腐敗がすすみ、化学反応によってガスが生じます。こうした消化管内のガスの一部は、血液に混じって呼気や皮膚呼吸によって体外に排出され、それ以外のガスもげっぷやおならとなって体外に排出されます。しかし、様々な理由でガスが発生しすぎると吸収や排泄が遅くなり、ガスが消化管内に溜まりすぎて腸などが膨らんでしまい、周辺を圧迫することで腹部膨満感が生じます。こうした状態を鼓腸とも言います。
ガス産生過剰
心因性
強いストレスを受けたり緊張したりすると奥歯を食いしばるようなタイプの方は、食事でもないのについ空気を飲み込んでしまいがちです。それが高じることで大量に空気を飲み込む呑気症という病気になることもあり、また過敏性腸症候群を発症することもあります。多量の空気によって消化管が膨らんでしまう現象から腹部膨満感を生じます。
腸内ガス産生の過剰
腸内細菌叢(腸内フローラ)が乱れてウェルシュ菌などの悪玉菌が増えてくると、食物の腐敗が進み、有毒物質を含むようなガスが多量に発生しやすくなります。
獣肉などの動物性たんぱく質、食物繊維などは身体に必要な栄養素の1つではありますが、偏りすぎないようにバランスを保って摂取する必要があります。
ガス排泄量低下
消化管、特に大腸の運動機能が低下することによって腸内で発生したガスが排泄されにくくなり、腹部膨満感があらわれます。それに伴って、便秘や過敏性腸症候群(便秘型や混合型)が発症することもあります。また、何らかの原因で腸閉塞が起こった時も腸内のガスを排出することができず、膨満感を生じることになります。
腹部膨満感が伴う病気
長期間膨満感が続いている場合、以下のような病気が原因かもしれません。
便秘
慢性的に便秘がある場合、便が腸内に溜まっている量が増えることや腸内滞留による腐敗でガスの発生が増えることなどから、膨満感が起こりやすくなります。
それだけでも身体の不調が起こりやすいのですが、便秘の原因が何らかの病気である可能性も考えられるため、一度当院の消化器内科にご相談ください。
腸閉塞
腸の手術痕の癒着、大腸がんなどによる腸管の極端な狭窄や癒着、運動機能障害による痙攣や捻れなどで腸管が詰まってしまい、便やガスが先へ進まない状況でイレウスとも言います。強い膨満感、嘔吐、腹痛といった症状があらわれ、早急な手当が必要になる可能性もありますのでお早めにご相談ください。
過敏性腸症候群
腹痛を伴う、便秘、下痢などの便通異常が続いている状況で、大腸に炎症や潰瘍、腫瘍といった器質的な病変が無い病気です。
大腸の運動機能や知覚機能に異常が生じている状態で、異常な膨満感やおならが止まらないといった症状をあらわすタイプもあります。生活習慣やストレスなども発症の引き金となりますので生活習慣を改善するとともに、薬物療法でつらい症状を抑えていきます。
呑気症
飲食の際に一緒にたくさんの空気を飲み込んでしまうことや、緊張すると奥歯を噛みしめて空気をのんでしまうなどが重なって、空気を消化管にとりこみすぎてしまう病気です。
空気の吸収や排出が間に合わず、胃や腸に膨満感を生じます。
逆流性食道炎
胃酸の混ざった胃の内容物が食道に逆流しやすくなって、食道粘膜が炎症をおこしてしまう病気です。
胸やけ、胃痛、げっぷや呑酸などの症状の他に、胃の膨満感、喉のつかえ、空咳などの症状があらわれることが特徴です。
以前は加齢による筋力の衰えが原因となる高齢者の病気というイメージでしたが、食生活の変化で若い層にも増えています。
お薬で比較的簡単に症状は治まりますが、再発を繰り返しやすく、食道がんのリスクも高まると考えられていますので、悪化させないよう気長に治療を続けていく必要があります。
急性胃腸炎
何らかの原因から胃腸が急激に炎症を起こしてしまっている状態で、腹痛、吐き気・嘔吐、下痢などと共に腹部膨満感を感じる方もいます。
原因としては、ウイルスや細菌による感染症が多く、その他には服用しているお薬による副作用などから起こることもあります。
機能性ディスペプシア
胃痛、胸やけ、腹部膨満感、早期飽満感(少し食べるとおなかがいっぱいになる)などの症状があらわれているのに、検査をしても上部消化管には炎症などの明らかな病変が見つからず、また内分泌的な異常も無いという場合に疑われる病気で、胃の運動機能や知覚機能に異常を起こしていることが原因で、過敏性腸症候群などと共に機能性胃腸障害に分類される病気です。
腹部の腫瘍
胃や大腸などの消化管、膵臓、女性の場合は卵巣などに腫瘍ができていると、腹部膨満感などの症状があらわれることがあります。
いずれのケースでも早期には自覚症状がほとんど無く、ある程度進行してから症状があらわれますので、定期的な健康診断が大切です。
上腸間膜動脈症候群
十二指腸付近で大動脈から枝分かれする上腸間膜動脈などの血管は周囲に脂肪が付着しており、他の臓器との間のクッションの役割を果たしています。
この脂肪が必要以上のダイエットなどが原因で無くなってしまうと、十二指腸などの臓器と血管が直接ぶつかることになり、腹部膨満感があらわれてしまいます。仰向けに寝ると症状が強くなり、うつ伏せ寝で症状が緩和するといった特徴があります。
腹部膨満感が続く場合は、
消化器専門外来を受診しましょう
一般的にはおなかの張りと表現される腹部膨満感は、食べ過ぎなどで一時的に起こっている場合もありますが、何らかの消化器の病気が原因となっている可能性もあります。特に、暴飲暴食などはっきりした理由がないのに急に膨満感を感じるようになった、ずっとおなかが張っている状態が続いているなどの場合は、念のため当院までご相談ください。
当院では消化器病を専門とする医師が、丁寧な問診と適切な検査によって原因をつきとめ治療方針をご提案しております。おなかの張りはなかなか患者様ご自身で説明することが難しい症状の1つですが、医師の方からうまく質問してまいりますのでご安心ください。