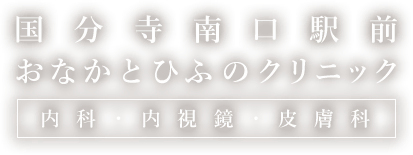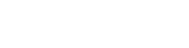腹痛の種類
腹痛は上腹部、左右の脇腹、下腹部などのおなか全体のどこかが痛むことです。痛みの原因は内臓痛と体性痛の2種類に分けることができます。
内臓痛
 内臓痛は、どこが痛いのかはっきりとせずおなか全体に鈍痛があらわれることが特徴です。胃や小腸、大腸などの消化管が急激に収縮したり、痙攣したり、拡張したりすることによって起こると考えられています。
内臓痛は、どこが痛いのかはっきりとせずおなか全体に鈍痛があらわれることが特徴です。胃や小腸、大腸などの消化管が急激に収縮したり、痙攣したり、拡張したりすることによって起こると考えられています。
内臓痛の代表的な例としては、急激に襲ってくる腹痛や、それに続く下痢などがあります。これは、ガスなどによって腸管の内圧が急激に高くなることで閉塞し、腸がひっぱられることで痛みが起こります。痛みと共に冷や汗や吐き気、嘔吐などがあらわれることもあります。
体性痛
 胃や腸の消化管や膵臓、肝臓などは、腹膜、腸間膜、横隔膜などによって構成される腹腔内にあり、外部の刺激から守られています。これらの生体膜や薄い筋肉などが炎症、または腫脹することで、知覚神経が刺激され痛みが起こるものが体性痛です。皮膚が傷ついた時と同様の痛みが生じます。一般的に、痛む場所がはっきりとしていて刺すような強い痛みが持続することが特徴です。
胃や腸の消化管や膵臓、肝臓などは、腹膜、腸間膜、横隔膜などによって構成される腹腔内にあり、外部の刺激から守られています。これらの生体膜や薄い筋肉などが炎症、または腫脹することで、知覚神経が刺激され痛みが起こるものが体性痛です。皮膚が傷ついた時と同様の痛みが生じます。一般的に、痛む場所がはっきりとしていて刺すような強い痛みが持続することが特徴です。
虫垂炎が悪化した際に生じる右下腹部の限られた部分の痛みが、この体性痛の代表的なものです。炎症が虫垂粘膜から腹膜などに及び、体性痛となります。
腹痛の原因
腹痛の原因として一般的に考えられるのは、胃や大腸の消化管と、膵臓、肝臓、胆嚢といった消化器、腎臓や膀胱、尿路などの泌尿器、子宮や卵巣、前立腺などの生殖器などの腹腔内臓器の異常です。
それ以外にも、心筋梗塞や狭心症といった循環器の病気によっても起こることがあります。これは、心臓と胃の知覚神経の脳への通り道が近いことによって、脳が勘違いしてしまうことから起こるものです。こうした痛みを関連痛と言います。
このような腹痛は早めに消化器内科・内科へ
- じっとしていられないほどの腹痛
- これまでに経験したことの無いおなかの痛み
- 前触れの無い突然の腹痛
- だんだんおなかの痛みが増してきた、いきなり痛みが強くなった
- おなかの痛みで安静にしていたが、回復しない状態が6時間以上続いている
- 腹痛だけでなく、嘔吐や吐血、下痢や血便(下血)、胸痛、発熱、冷や汗や震え、意識低下などがある
- 内臓を絞られるような痛みの腹痛
腹痛の原因と症状を伴う病気
機能性ディスペプシア
 胃痛、胸やけ、早期飽満感(食べ始めてすぐにおなかがいっぱいになってしまう)などの上部消化管の症状があるのに対して、検査をしても炎症、潰瘍、腫瘍といった器質的な病変や内分泌的な異常が見つからない病気です。胃の運動機能や知覚機能になんらかの障害が起こっていることが原因となっています。胃の運動機能改善薬、胃酸分泌抑制薬などの他、ストレスなどの精神的要因が強い場合は抗不安薬などを一時的に処方することもあります。
胃痛、胸やけ、早期飽満感(食べ始めてすぐにおなかがいっぱいになってしまう)などの上部消化管の症状があるのに対して、検査をしても炎症、潰瘍、腫瘍といった器質的な病変や内分泌的な異常が見つからない病気です。胃の運動機能や知覚機能になんらかの障害が起こっていることが原因となっています。胃の運動機能改善薬、胃酸分泌抑制薬などの他、ストレスなどの精神的要因が強い場合は抗不安薬などを一時的に処方することもあります。
胃・十二指腸潰瘍
胃や十二指腸の粘膜が胃酸による攻撃によって深くえぐれてしまっている状態です。みぞおちの痛み、吐き気や嘔吐などの症状があらわれます。進行すると、消化管壁の血管が障害されて出血することがあり、吐血や下血(黒色便)となってあらわれます。さらに進行すると胃壁や十二指腸壁に穴があく穿孔を起こす可能性もあります。
逆流性食道炎
食道に強い胃酸を含んだ胃の内容物が逆流し、それが長期的に滞留することで食道粘膜に炎症が起こってしまう状態です。みぞおちの痛みに加え、げっぷ、呑酸、喉の詰まりといった症状があらわれます。
虫垂炎(盲腸)
 盲腸とも呼ばれることがある虫垂炎は、盲腸の先に紐のように飛び出した虫垂に便などが入り込んで炎症を起こしてしまう状態です。初期には、みぞおちの痛みと共に吐き気などの症状があり、徐々に痛みが移動して最終的には右下腹部に強い痛みを生じます。
盲腸とも呼ばれることがある虫垂炎は、盲腸の先に紐のように飛び出した虫垂に便などが入り込んで炎症を起こしてしまう状態です。初期には、みぞおちの痛みと共に吐き気などの症状があり、徐々に痛みが移動して最終的には右下腹部に強い痛みを生じます。
近年では、抗菌薬の投与による治療が優先となりましたが、腹膜まで炎症が起こるなど進行している場合には手術が必要となります。その場合、当院と連携する高度医療機関を紹介し、スムーズに治療を受けていただけるようにしています。
急性膵炎
消化を助ける膵液を産生する膵臓が、急激に炎症を起こした状態です。
原因としては、胆石や飲酒が挙げられます。みぞおちから臍・背中にかけて広範囲に強い痛みがあります。
過敏性腸症候群
消化器に、器質的な病変や内分泌異常などが見当たらないのに対し、長期間の腹痛を伴う便通異常が起こる病気です。
大腸の運動機能・知覚機能の障害が原因です。機能性ディスペプシアなどと共に、機能性消化器疾患に分類されています。
感染性胃腸炎(ノロウイルス/カンピロバクター等)
ウイルスや細菌、細菌が産生した毒素に感染することで、胃腸の広範囲に炎症が起こります。
腹痛、嘔吐、下痢、発熱などがあらわれます。
主な病原体は、ノロウイルスやロタウイルス、カンピロバクター、黄色ブドウ球菌、病原性大腸菌などで、夏は細菌、冬はウイルス感染が多い傾向があります。
便秘
大腸の運動機能や知覚機能の低下、腸管の狭窄などの物理的な障害から、便が数日出ない状態や、出ても残便感などがあり満足できない状態を便秘と言います。
腹痛や腹部膨満感などの腹部症状を伴うことも多く、慢性的に続く場合は何らかの器質的な病気による可能性もあるため、しっかりと原因を特定して適切な治療を行うことが大切です。
大腸憩室
大腸の粘膜が、筋層の消失と腸管内圧の上昇によって漿膜側(腸管の一番外)に風船のように凹んでできた空洞が大腸憩室です。そのままであれば特に問題はないのですが、便が詰まって炎症を起こしたり(大腸憩室炎)、凹んだ部分が血管を刺激して出血したり(大腸憩室出血)することもあります。
大腸憩室炎は、腹痛を伴うことが多いのですが、大腸憩室出血の場合は痛みを伴わず、突然の大量の血便があらわれるため、注意が必要です。
大腸がん
長年、大腸ポリープを放置した部分ががん化する例が多いです。
早期のうちはほとんど自覚症状がありませんが、進行してくると便通異常や便潜血、血便などとともに、腹痛などの症状があらわれることもあります。
炎症性腸疾患
腸に炎症を起こす病気の総称ですが、一般的にはクローン病や潰瘍性大腸炎などの自己免疫疾患が疑われる、非特異的炎症性腸疾患を示すことが多くなっています。
どちらも、慢性的に腸の炎症が起こり、びらん、潰瘍などによって腹痛や粘血便などの症状があらわれます。確立された完治方法が見つかっておらず、国の指定難病になっています。
腹痛の検査
腹痛がある場合、原因となる病気を問診や触診などから推測し、それに応じて必要な検査を行うことになります。
血液検査、便検査、尿検査などの他、腹部超音波検査なども行いますが、特に重要になるのが胃カメラ検査と大腸カメラ検査です。
胃カメラ検査
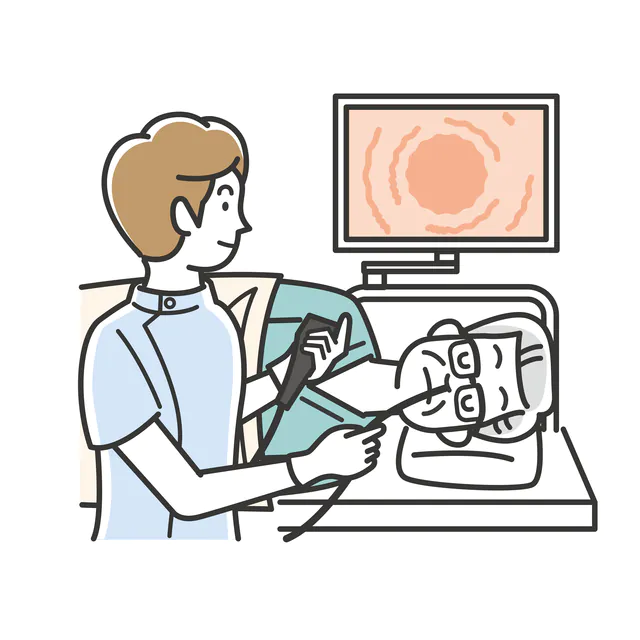 胃カメラ検査は、スコープと呼ばれる検査装置を口または鼻から挿入し、喉、食道、胃、十二指腸の粘膜の状態を、医師が直接的に観察することができます。粘膜の炎症、びらん、潰瘍、腫瘍等の病変が無いかを目視で確認できる他、疑わしい病変があれば細胞を採取して病理検査を行い、確定診断に導くこともできます。また、出血などがあった場合には止血処置を行ったり、アニサキス症が起こっている場合にはアニサキスを排除したりすることができるなど、診察、診断、治療など様々な点で有用な検査です。
胃カメラ検査は、スコープと呼ばれる検査装置を口または鼻から挿入し、喉、食道、胃、十二指腸の粘膜の状態を、医師が直接的に観察することができます。粘膜の炎症、びらん、潰瘍、腫瘍等の病変が無いかを目視で確認できる他、疑わしい病変があれば細胞を採取して病理検査を行い、確定診断に導くこともできます。また、出血などがあった場合には止血処置を行ったり、アニサキス症が起こっている場合にはアニサキスを排除したりすることができるなど、診察、診断、治療など様々な点で有用な検査です。
大腸カメラ検査
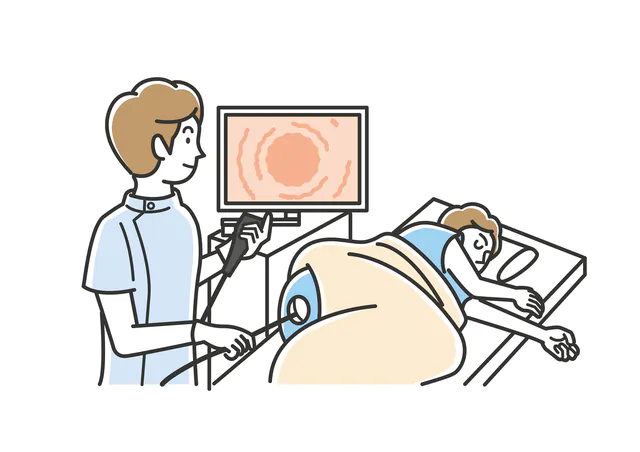 お臍の辺りや下腹部などに痛みがあり、血便、腹部膨満感、下痢、便秘等の下腹部の症状がある場合は大腸カメラ検査が有用です。
お臍の辺りや下腹部などに痛みがあり、血便、腹部膨満感、下痢、便秘等の下腹部の症状がある場合は大腸カメラ検査が有用です。
大腸カメラ検査は、スコープと呼ばれる検査装置を肛門から挿入し、大腸全体の粘膜を細かく観察することができます。これによって、大腸粘膜の炎症やびらん、潰瘍、腫瘍といった器質的な病変の位置や程度を特定できるだけではなく、疑わしい病変の細胞を採取し病理検査を行うことや、出血などがある場合の止血処置、前がん病変である大腸ポリープ切除を行うことも可能です。つまり、大腸カメラ検査は、1度に検査、診断、治療、予防までが可能な検査ということができます。
苦しくない胃カメラ・大腸カメラ検査
 以前は、苦しい、辛いと言われる胃カメラ検査、大腸カメラ検査でしたが、当院ではこれらの検査の知見と手技を特別に認められた医師が、患者様の負担を最低減に抑える検査を行っています。
以前は、苦しい、辛いと言われる胃カメラ検査、大腸カメラ検査でしたが、当院ではこれらの検査の知見と手技を特別に認められた医師が、患者様の負担を最低減に抑える検査を行っています。
腹痛などの消化器の不調がある方は、ぜひ当院までご相談ください。